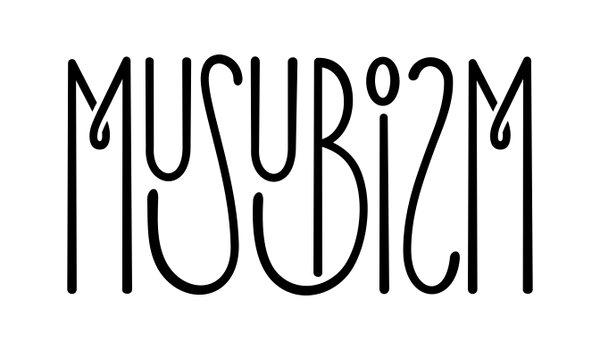風呂敷との出会い
私は幼少期を含めてヨーロッパで7年、香港で2年暮らしました。その間、日本文化と西洋文化の違いを肌で感じることが増えていきました。風呂敷は、私にとってお茶会で和服を着るときに荷物や小物をまとめるための布でした。それ以上の意味を深く考えたことはなかったです。けれども、異国の地で暮らすうちに、日本の伝統文化には 「西洋にはない何か」 があることに気づき始めました。風呂敷もまた、そのひとつなのかもしれないと感じるようになりました。

「すべてを変えた瞬間」
ある日、外国人の友人と京都を旅していたときのことです。ふと立ち寄ったお店で、私は一枚の風呂敷に目を奪われました。日本の伝統的な鶴の柄をモチーフにしながらも、洗練されたデザインのコットンの風呂敷。「なんて美しく、おしゃれなんだろう」その瞬間、風呂敷が持つ無限の可能性を感じました。格式ばったものでも、和服専用のものでもない。ジーンズにも合うもっとカジュアルで、自由に、美しく楽しめるものだったのです。このとき、風呂敷が日本の伝統と現代をつなぐアイテムになりうる ことを実感しました。そこから風呂敷への興味がどんどん広がっていきました。

素材が変える、風呂敷の使い方
風呂敷について知れば知るほど、その奥深さに気づきました。絹の風呂敷は、見た目の美しさが格別で、特別なシーンを華やかに彩ります。一方で、木綿の風呂敷は軽やかで丈夫。洗濯機で洗うこともでき、毎日の暮らしに馴染みます。風呂敷をもっと 日常のアイテムとして取り入れたい という思いが、どんどん膨らんでいきました。ふろしきは質感以上のもの、物語を伝える媒体、過去と現在を織り交ぜる手段だと考えるようになりました。自分のふろしきを作りたいという思いが芽生えていきました。

「使う側」から「創る側」へ
絹の風呂敷は、見た目の美しさが格別で、特別なシーンを華やかに彩ります。一方で、木綿の風呂敷は軽やかで丈夫。洗濯機で洗うこともでき、毎日の暮らしに馴染みます。風呂敷をもっと 日常のアイテムとして取り入れたい という思いが、どんどん膨らんでいきました。自分の風呂敷を創りたいいつしか私は、風呂敷を「使う側」から「創る側」へと変わっていました。最初は、ユザワヤで好みの布を買い、端を縫うところから始めました。次第に 「もっと使いやすい生地で、自分だけのデザインを作りたい」 と思うようになりました。デザインを描き、実際の製作工程を学ぶ中で、その奥深さに感動しました。風呂敷の染めは、江戸時代の浮世絵の版画のように、何層にも分けて色を重ねて表現されます。使える色数に限りがあるなかで、日本の着物の配色センスが大きなヒントになりました。鮮やかな色と、それを引き立てる淡い色との絶妙なバランス。この日本独特の美しさを、風呂敷で表現できたらどんなに素敵だろう。そう考えながら、一枚一枚のデザインを仕上げています。

ふろしきが私の「安心感」になる
もうひとつ、私が大切にしているのが「自分らしさ」です。趣味の登山では、山小屋やテントに泊まることがよくあります。そんなとき、風呂敷は私の心を「安心感」で包んでくれる存在 なのです。登山道具は、機能性を追求するため、無機質な色やデザインのものが多い。そのなかで、お気に入りの柄の風呂敷があるだけで、なんか心が落ち着きます。荷物をまとめたり、小物を入れるバッグを作ったり、寝るときには枕カバーとして使ったり——。見知らぬ場所にいるときも、雪洞の中で眠るときも、風呂敷の温もりが心を落ち着かせてくれる。そんな小さな安心感が、どれほど大切かを実感するようになりました。

職人との出会い、手仕事への感動
風呂敷づくりを進めるうちに、私は 職人さんのひたむきな姿勢 に深く感銘を受けました。皆さん、40年以上もの間、ひたすら良いものを作り続けてきた。昨日よりも今日、今日よりも明日、もっと良いものを届けたい。その強い思いを持ちながら、手仕事を貫き続けているのです。その想いはただの技術ではなく、生き方そのものだと感じます。風呂敷はただの布ではなく、一枚一枚に職人の魂が込められています。職人の息づかい、こだわり、そして誇りが刻まれています。そんな彼らとともに、風呂敷の新しい可能性を追求し続けたい。日本の伝統を大切にしながら、現代のライフスタイルにも調和する風呂敷。環境にやさしく、使うほどに愛着が増し、暮らしに寄り添うものを作りたい。それが、私の原点です

「横浜捺染で自分のルーツを見つける」
ふろしき作りの奥深くへと足を踏み入れていくうちに、思いがけない発見がありました。故郷の豊かな染色の歴史です。120年前、横浜捺染は伝統技術の限界を押し広げ、一大産業として台頭しました。まさに職人技と革新が融合した場所でした。私が今日作っているのは、過去と未来をつなぐ橋です。

「お茶とふろしきの心」
茶の湯の世界には「一期一会」という言葉があります。一度きりの出会いを大切にする心。一碗のお茶の中に、亭主と客の心が込められています。ひとつひとつの所作には意味があり、今この瞬間に心を澄ませ、互いに向き合い、心と心を通わせる。その静けさの中に、深い豊かさがあると感じます。
私は今も修行中の身ではありますが、稽古を重ねるたびに、その奥深さに心を動かされます。ひとつひとつの動き、呼吸のひとつにも、静かな意図と美意識が宿っていることに気づかされます。
そして、ふろしきもまた、同じ心が宿っています。一枚のふろしきが、贈る人と受け取る人の想いをつなぐ。ひとつの結びに、言葉にならないやさしさが込められる。ふろしきを通して、誰かと心が通い合うこと。そして、その一瞬をそっと包み、大切にすること。それこそが、私がふろしきに託したい想いです。
「未来へのふろしき」
私はこれまで、いくつもの不思議なご縁に導かれるように、ここまでたどり着きました。「無謀」と言われながらも出会った人たち、心が動いた瞬間の一つひとつが「結び」となり、ようやく“はじまり”に立っているような気がしています。
この先、どんな物語が待っているのかわかりませんが、自分を信じて進むだけです。ふろしきが、世界中の心と心をそっと結んでくれる未来を。
ふろしきに託された結びには、いつだって物語があるから。
——これは、私の物語です。