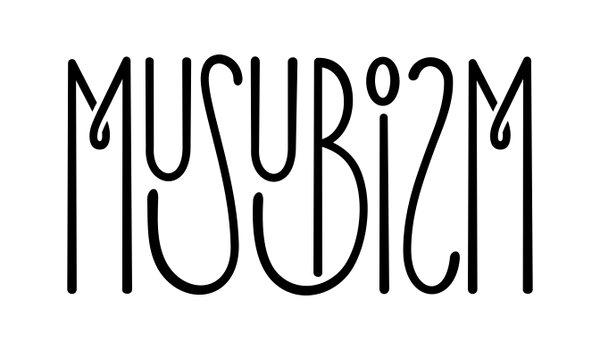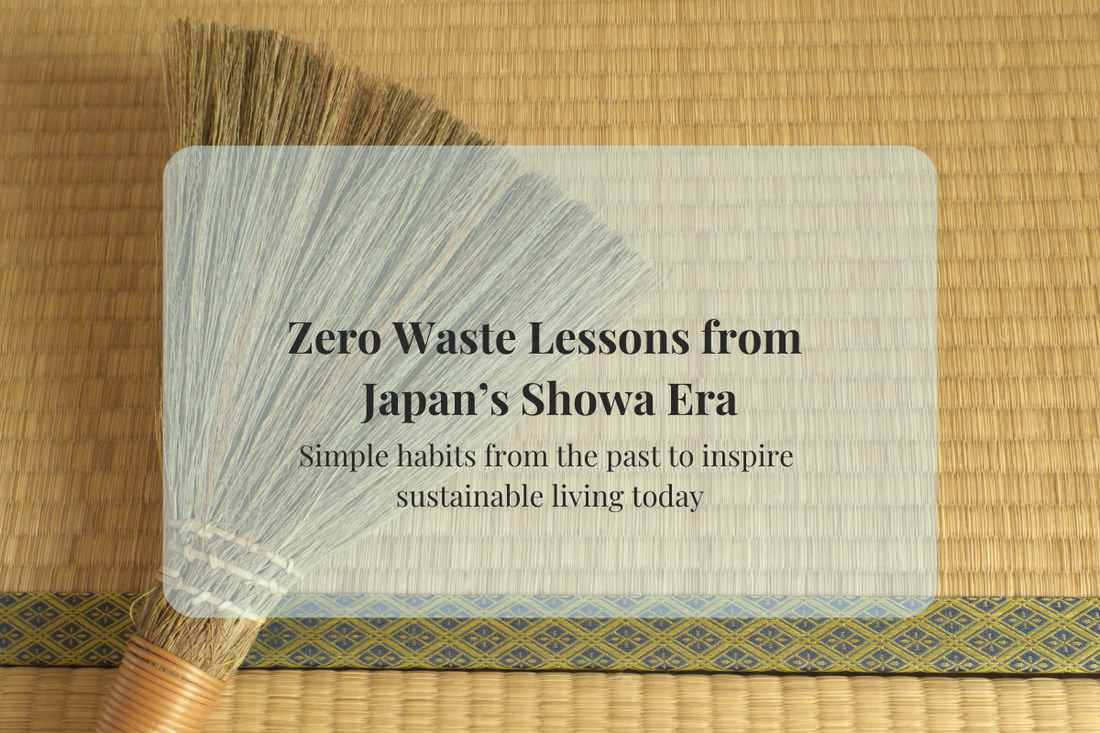
昭和の暮らしに学ぶ、エコで無駄のない工夫
子供の頃、私は祖父母の家で暮らした時期があります。思い出すのは、祖母が茶がらを畳に撒いて箒で掃除していた姿です。掃除機はありましたが、畳の部屋はそのほうが良いというこだわりがありました。使わなくなった手拭いを刺し子で縫って雑巾にし、縁側の廊下を拭く。窓ガラスは湿らせた新聞紙で磨くときれいになると言って、私もよく手伝わされました。
祖父は自転車が好きで、大切に扱っていました。パンクは自分で直し、チェーンには油を差して調整し、ボディは刺し子の雑巾でいつもピカピカに磨いていました。
あの頃の昭和の暮らしには「ゼロウェイスト」や「サステナブル」といった言葉はありませんでした。それでも自然と無駄を減らす工夫が生活の中にありました。物を買うのが簡単ではなかったからこそ、工夫して長く使い切ることが当たり前だったのです。
掃除や再利用
- 茶がらを畳に撒いて掃くと埃が舞わず香りも残る
- 湿らせた新聞紙で窓を拭けばピカピカに
- 古布は雑巾に縫い直して最後まで使う
台所の工夫
- 野菜の皮やくずは漬物や出汁に利用
- 米のとぎ汁は床磨きや植木の水やりに
- 干物や味噌漬けで保存
- お味噌や梅干しは祖母の手作りで、亡くなるまで我が家では買ったことがなかった
冷凍食品に頼らなくても、工夫と季節の知恵で食卓は整っていました。
燃料とエネルギー
- 祖父は七輪で焼き魚を楽しむのが好きだった
- 使った炭の余熱で煮込みや保温に活用
- 夏は打ち水やすだれ、風通しで涼しく過ごした
衣類と布
- 着物は仕立て直して代々使う
- 破れは刺し子や継ぎ当てで補修
- 最後は雑巾やおむつとして布を使い切る
暮らしの道具
- 木や竹の道具は壊れれば修理して長く使う
- ざるや籠は役目を終えたら燃料や土に返す
- 道具を自然に循環させる発想があった
現代の暮らしとの対比
今の生活は、物がすぐに手に入るのが当たり前になりました。スマホで注文すれば翌日に届き、少し遅れただけで不満を口にする人もいます。便利さは増しましたが、その一方で物を大切に扱う感覚は薄れているように感じます。
私が育った時代は、買うより工夫して使うのが自然でした。布は最後まで使い切り、壊れた道具は直して長く使いました。食べ物は保存や発酵の知恵で無駄なく消費しました。今で言う「ゼロウェイスト」の考え方を、意識せずに実践していたのです。
結び
昭和の暮らしには、物を大切にし、無駄を出さない工夫がたくさんありました。それは貧しさから生まれた知恵でもありますが、同時に自然と共に生きる知恵でもありました。
便利さに慣れた今の生活に、あの頃の工夫を無理なく少し取り入れるだけで、暮らしは変わります。米のとぎ汁を植木にやる、布を最後まで使い切る、打ち水をして涼をとる。どれも大きな負担ではなく、生活に心地よさを与えてくれる方法です。
風呂敷のすすめ
そして忘れてはいけないのが風呂敷です。一枚あれば荷物を包んだり、バッグ代わりにしたり、テーブルクロスや収納にも使えます。普段は小さく畳んで持ち歩け、繰り返し使えて捨てる必要もありません。
日本は自然災害の多い国です。災害時には荷物をまとめたり、避難所での目隠しや、怪我をしたときの三角巾としても役立ちます。普段から持ち歩いていれば、いざというとき心強い道具になります。
昔の知恵は過去のものではなく、これからの時代にこそ役立ちます。風呂敷のように、ひとつで何通りもの役割を果たす工夫を暮らしに取り入れながら、毎日を少し豊かに、安心して過ごしてみませんか。