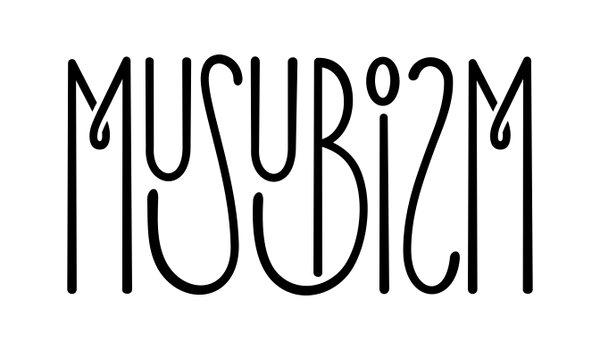ふろしきで包む、こころを贈る——日本の美意識が息づく手土産のかたち
週末の夕暮れ、同僚の家に招かれて向かう道すがら。
手にしたのは、赤と白のワイン——それらを1枚のふろしきで、丁寧に「瓶二本包み」で包みました。
たった一枚の布が、手土産の印象をぐっと格上げしてくれる。そんな小さな工夫を、私はとても大切にしています。
包むということ、それは日本ではひとつの“礼”です
多くの国で、ギフトラッピングは「飾る」「隠す」ためのもの。
でも日本では、「包む」という行為そのものが思いやりの表現とされています。
ふろしきで贈り物を包むことは、
「あなたのことを想い、この時間を用意しました」という静かなメッセージ。
それはまさに、日本文化が大切にしてきた、相手への敬意と心配りの象徴です。
近年では、このような感覚が海外の研究者たちからも注目されています。関西外国語大学の熊谷映子氏は、日本人の日常に息づく“無意識のホスピタリティ”に着目し、その文化的意義を論じています¹。
機能を超えて、心に残るふろしき
ふろしきは実用的です。
一度使えば、またスカーフやバッグ、エコラップとして繰り返し使える。
けれど、本当の魅力は、その包み方が相手の記憶に残るというところにあります。
その晩、ふろしきで包んだワインを渡すと、同僚は目を見張り、
「これ、ふろしき?すごく素敵」と笑顔を見せてくれました。
何を贈るかだけでなく、“どう贈るか”が人の心に届くことを、改めて感じた瞬間です。
ふろしきという哲学——布に宿る、やさしい間合い
韓国のポジャギや、ヨーロッパのファブリックギフトバッグなど、世界には美しい包み文化がたくさんあります。
でも日本のふろしきには、贈る人と受け取る人の間に「間(ま)」をつくるという特別な美意識が流れています。
折り目、結び方、柄の選び方——そのすべてが、相手を想う心の設計。
その繊細な間合いが、日本文化の静かな哲学として、今も私たちの暮らしに息づいています。
ふろしきを選ぶということ
次に誰かを訪ねるとき、紙袋ではなくふろしきを使ってみてください。
それは、サステナブルで美しいだけでなく、ほんの少し暮らしを丁寧にしてくれる選択です。
そして何より、それを受け取った人が、また誰かにふろしきを使ってくれたら——
その布は、ただの包みではなく、人と人との想いを巡らせる「こころの器」となるのかもしれません。
参考文献
¹ 熊谷映子『日本におけるホスピタリティの文化的考察―無意識のホスピタリティについて―』関西外国語大学 研究紀要 第121号
PDFはこちら