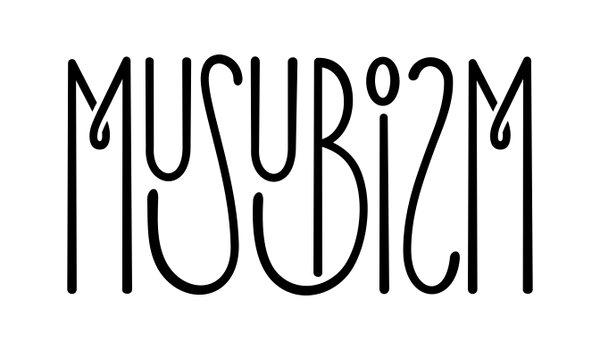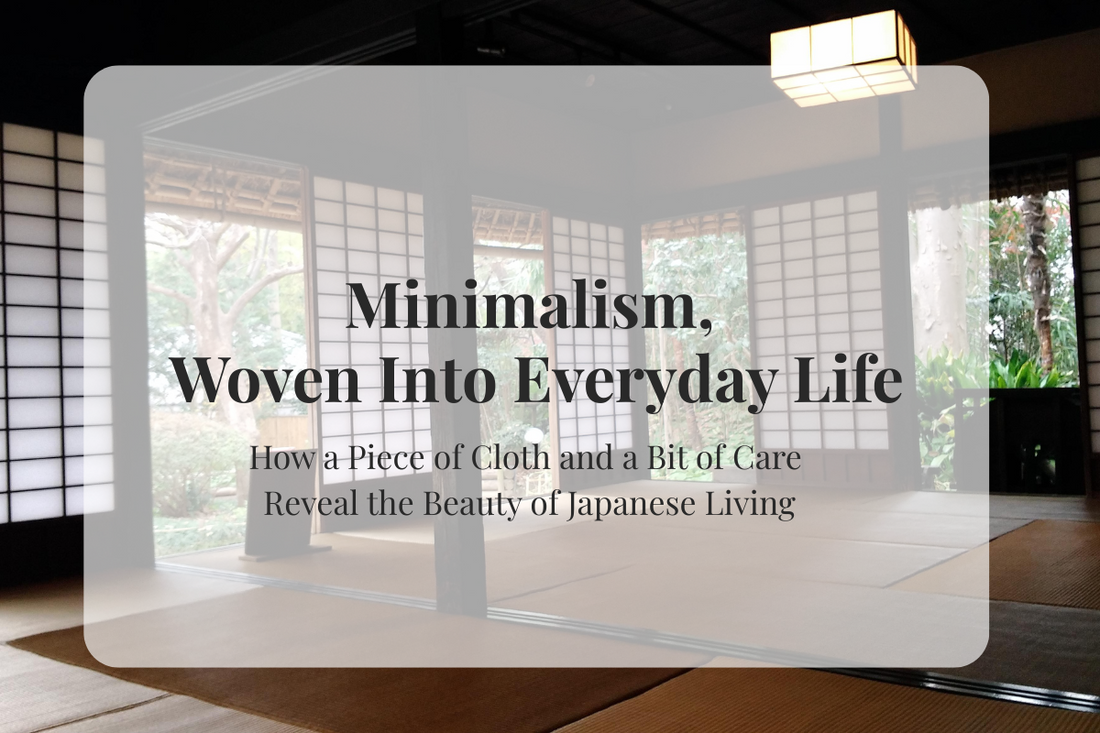
ミニマリズムは、祖母の日常にあった。
風呂敷と、日本人の暮らしの美意識
掃除機はあったのに、祖母は使いませんでした。
畳にお茶がらを撒き、箒で掃く。すると、畳の目に入り込んだほこりがしっかりと取れる。
今なら「エコ掃除」や「サステナブルな暮らし」と呼ばれるようなことを、祖母は自然に行っていたのです。
日本の暮らしには、ミニマリズムの思想が根付いていたと思います。
「買う」前に「選ぶ」ことから始まる、暮らしの質
ネットショッピングは便利です。
ワンクリックで何でも届く現代、私たちは“手に入れる”ことに慣れすぎているのかもしれません。
けれど、本当に必要なものは何か?
そう問い直すとき、暮らしの姿勢が変わっていきます。
たとえば私は、スーパーでの買い物を風呂敷に入る分だけに決めています。
カートではなく買い物かごを持ち、買ったものを自分で持って帰る。
こうすると、自然と「本当に必要なもの」だけを選ぶようになるのです。
最後まで使い切る知恵
縁側の掃除は、いらなくなったタオルで作った雑巾。
ぴかぴかになるまで使って、役目を終えてから手放す。
最近、我が家の床の黒積みを重曹とセスキで磨いてお掃除しました。
使ったのは要らなくなった古い風呂敷でした。
長年タンスに眠っていた、微かに黄ばんだ布。
もう使えませんが、最後に掃除布として働いてくれて、感謝の気持ちで手放すことができました。
道具を生み出す「ひと手間」の楽しさ
風呂敷は、ただの布から、結びひとつで袋になり、
肩掛けにも、リュックにも変身します。
その時々の工夫で「道具」に変わる柔軟さ。
ことばがなかった時代、人はこうして道具を作り、使いこなしてきたのです。
ひと手間をかけるからこそ、愛着が湧く。
そして、その“手間”は、心のゆとりを生み出してくれて、楽しいものでもあります。
今こそ、風呂敷のある暮らしを。
コンビニの冷やし中華を食べたあとに残る、美しくも複雑なパッケージ。
麺と具が別々の2段式、スープや調味料は別のパッケージに。
手軽な便利さの裏側で、またゴミを“消費した”という感覚が残ります。
もちろん、手を抜く日があってもいい。
風呂敷に包んだお弁当を作って持っていけば、健康にも、財布にも、環境にもいいわけです。
すこしだけ立ち止まって考えてみませんか?
もし、ひとりひとりが「風呂敷に入る分だけ」と意識して暮らせば、
その分だけ、世界からゴミが減るかもしれません。
暮らしを選ぶ、という豊かさ
おばあちゃんの知恵のような暮らし方には、
無駄を省き、本当に必要なものを大切にする“心のミニマリズム”が宿っています。
風呂敷は、それを思い出させてくれる日用品です。
モノを選ぶ目、道具を使い切る知恵、そして手間の中にある工夫という楽しさ。
今の暮らしに、もう一度取り入れてみませんか?