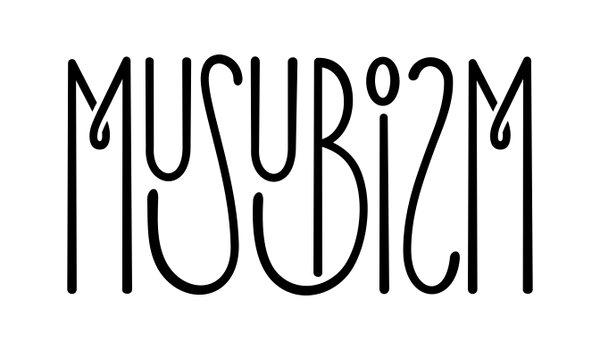ふろしきに映る日本の美意識
人は、その人の心の美しさに触れた時に感動するのです。
それは人だけでなく、国にも当てはまるように思います。
海外から日本がほめられる理由は、日常の中にあります。
朝の道が清潔であること。お店の前を店主が掃いていること。
駅で人が自然に列を作ること。
公園のゴミ箱がいっぱいでも、持ち帰る人がいること。
こうした一つ一つが、日本らしい美しさをつくっています。
落とし物が戻ってくることも、よくある話です。
財布や定期券だけでなく、子どもの手袋まで丁寧に届けられる。
駅では忘れられた傘が束ねられ、持ち主が見つけやすいように立てかけられています。
誰かのために、少し手をかける。そうした行いが積み重なっています。
夜の街でも、さりげない思いやりがあります。
困っている人に声をかける。暗い道を避けて歩く。
小さな気づかいが、安心を生みます。
子どもが一人で通学できるのも、社会全体の信頼があるからです。
地域の大人が見守り、道ですれ違えば挨拶を交わす。
学校も家庭も、思いやりを教える。
そうして、人と人との間に目に見えない安心の糸が張られています。
災害の時には、秩序ある行動が印象に残ります。
配給の列が静かに進み、必要な分だけを受け取る。
誰かが困っていれば、すぐに譲る。
それは感情を抑えているのではなく、互いを思う心が自然に表れているのです。
明治の時代、日本を訪れたラフカディオ・ハーンはこう書いています。
“Japanese affection is not uttered in words; it scarcely appears even in the tone of voice; it is chiefly shown in acts of exquisite courtesy and kindness.”
(「日本人の愛情は言葉ではなく、声の調子にもあまり表れない。それは繊細な礼儀と優しさという行いの中に現れる」)
※出典: Lafcadio Hearn, Japan: An Attempt at Interpretation (1904)
日本の美しさは、飾るより整える、見せるより守る、語るより行う、というところにあります。
掃く、並ぶ、譲る、包む。どれも大げさではなく、日常の動きの中にあります。
その象徴が「ふろしき」です。
ふろしきは、ものを包むための布ですが、心を形にする道具でもあります。
贈り物を包むとき、箱をそのまま渡さず、布で包み、結び目を少しずらします。
相手が開けやすいように向きを考え、手に取りやすく整える。
受け取る人の時間まで想像する、その気づかいが礼になります。
買い物袋の代わりにふろしきを使う人も増えました。
瓶を二本包む「瓶二本包み」は、持ち手が自然に手になじみます。
急な雨が降れば、荷物の防水にもなります。
その柔らかさと融通の利く形が、無駄を減らし、暮らしを整えます。
誰かの持ち物をふろしきの上にまとめて置く。
それだけでも、「気にかけています」という気持ちが伝わります。
言葉よりも、行いで表す美しさです。
結び方にも意味があります。
「真結び」はほどけにくく、ほどきやすい。
結び目を相手の方に向けて軽く引くと、すっと開く。
強すぎず、弱すぎない。人との関係にも通じます。
使い終えたふろしきは、畳んでまたしまう。
一枚の布が、何度も形を変えて働き、また戻る。
長く使ううちに、手になじみ、風合いが出ていきます。
そこに時間の美しさがあります。
日本の美意識は、派手さの中にはありません。
日常の小さな所作の中に、静かに息づいています。
ふろしきは、その心を今に伝える小さな布です。
手に取るたびに、誰かの思いやりが重なっていくように感じます。