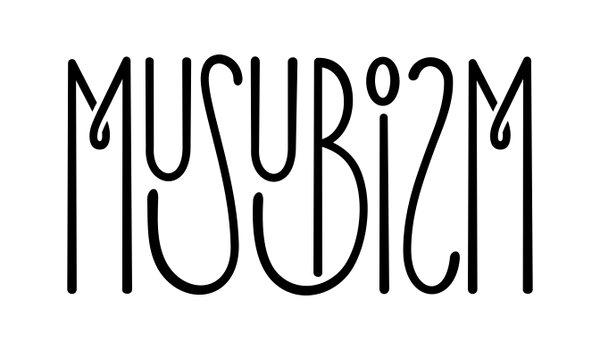なぜ「包む」のか。
風呂敷が教えてくれた心の形
人は、誰も最初は裸で生まれます。
けれど、生まれる前からずっと包まれています。
母親のお腹の中で、やわらかな羊水と身体に包まれ、守られながら育ちます。
「包む」という字は、その姿を表したものだと言われています。
胎児をお腹の中で抱いている形。
それが「包」という文字のはじまりです。
生まれた瞬間、赤ちゃんは初めて外の世界の風に触れます。
その瞬間に、母親の手で布や服に包まれます。
それが人生で最初の「お包み」です。
その手の温もりには、守りたい、温めたい、育てたいという思いがこもっています。
そして人生の終わりにも、人は包まれて旅立ちます。
大切にしてきたものや衣に包まれ、穏やかに眠りにつきます。
それは、その人の生き方をそっと包み込む「最後のお包み」です。
包むという行為は、始まりから終わりまで、人の心とともにあります。
風呂敷は、その心を形にできる日本の文化です。
手をかけて包み、それを結ぶ。
その一手間には、相手を思う心、自分を整える時間、自然を大切にする気づきが込められています。
風呂敷は、繰り返し使える布です。
けれど、それ以上に「人を思い、包む心」を伝えてくれるものです。
手で包むとき、人は誰かを大切に思う気持ちを取り戻します。
その瞬間、母のお腹にいたあの安心感のようなものが、ふと蘇るように思います。
風呂敷っていいものだなと思います。
そして、これからも「包む」という日本の美しい心を伝えていきたいと思います。