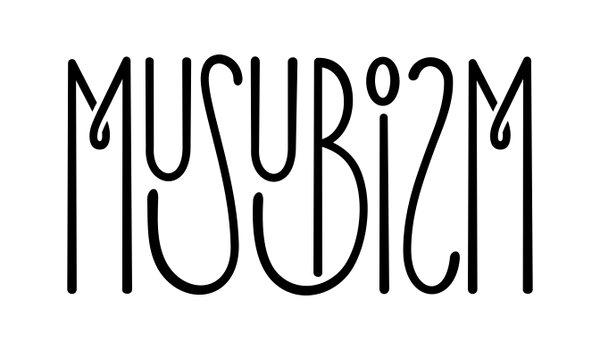贈ることの美しさ― 贈り物と所作と文化が一つになるとき ―
包むということは、想いを伝えること ― 風呂敷と歩んだ10年
風呂敷は、時代や場所によって自然にその形を変えていくものかもしれません。
けれど知れば知るほど、それは単なる布ではなく、日本人の精神や美意識が織り込まれた、深い意味を持つ存在だと感じるようになりました。
風呂敷との出会い
私が風呂敷に出会ったのは、約10年前、京都でのことでした。
やわらかな手触り、美しい色と柄、そして何よりも「包む」という所作に込められた優しさや心づかいに、強く心を打たれました。
それをきっかけに、風呂敷について調べ始め、職人さんのもとを訪ね、お話を伺い、自分でも風呂敷を作るようになりました。
気づけば、あれから10年が経とうとしています。
世界に広がる「包む布」文化
風呂敷は日本独自の文化ですが、「包む布」は世界各地にも存在します。
その土地の暮らしや精神性を映し出すように、それぞれの文化が息づいています。
たとえば:
-
ポジャギ(韓国)
絹や麻をパッチワークに仕立てた布。「福を包む」という意味があり、贈答や装飾として使われています。 -
カンガ(東アフリカ)
鮮やかな色彩とスワヒリ語の格言が特徴。衣服や贈り物、メッセージの伝達手段としても機能しています。 -
アグアヨ/マンタ(南米)
アンデス地方の人々が物や子どもを運ぶために使う布。織りや模様に地域性があり、文化を反映しています。
これらの布はいずれも、単なる道具ではなく、文化や物語、美意識が織り込まれた存在です。
風呂敷もまた、日本の調和・思いやり・簡素の美を体現しているのだと思います。
表面だけでは伝わらないもの
近年、風呂敷は「サステナブルで美しい日本文化」として海外でも注目されるようになりました。
それ自体はとても喜ばしいことですが、同時に懸念も感じています。
「日本製」として売られているものの中には、実際は海外で大量生産されたものもあり、
「手捺染」と謳いながら、実は機械印刷で作られたものも見受けられます。
一見すると伝統的な風呂敷に見えても、その背景にある職人の手仕事、込められた意図、文化的な精神は、まったく異なるものです。
その違いを見つめ、丁寧に伝えていくことは、
手仕事を愛し、本物を大切にする者としての大切なことだと思っています。
同時に、私たちは今、それとは逆行するように歩んでいます。
小さな工房が、ひとつまたひとつと静かに消えていっているのです。
それもまた、グローバル化と効率重視の経済の中では自然の流れなのかもしれません。
けれど私が最初に心を奪われた、あの静かで力強い手仕事の美しさは、今もきっと、多くの人の心に響くはずだと信じています。
だからこそ私は今日も活動を続けています。
その手に宿る精神と、そこから生まれた物語が、誰かの心に届くことを願って。
「包結道(ほうけつどう)」という考え方
このような想いから、私は風呂敷を単なる商品としてではなく、文化的な哲学として伝えることを目指すようになりました。それが私の提唱する「包結道(ほうけつどう)」です。
“包む”という行為は、相手を思う心のかたち。
それは、人との関係性や、自分自身との向き合い方を映し出す静かな所作です。
慌ただしい時代だからこそ、包むという行為は、
モノや人、そして意味とのつながりをもう一度見つめ直すきっかけをくれるのではないでしょうか。
おわりに
風呂敷には、職人の手から生まれた温もりがあり、
それを使う人の心が重なることで、豊かな表現が生まれます。
贈ること、包むこと、その所作の中に、日本ならではの繊細さと優しさが息づいています。
これからも私は、この文化をできる限り丁寧に、誠実に伝えていきたい。
それが、風呂敷に魅せられた一人としての願いです。
参考リンク
ポジャギ(Bojagi) – Wikipedia
カンガ(Kanga) – Wikipedia
アグアヨ(Aguayo) – Wikipedia